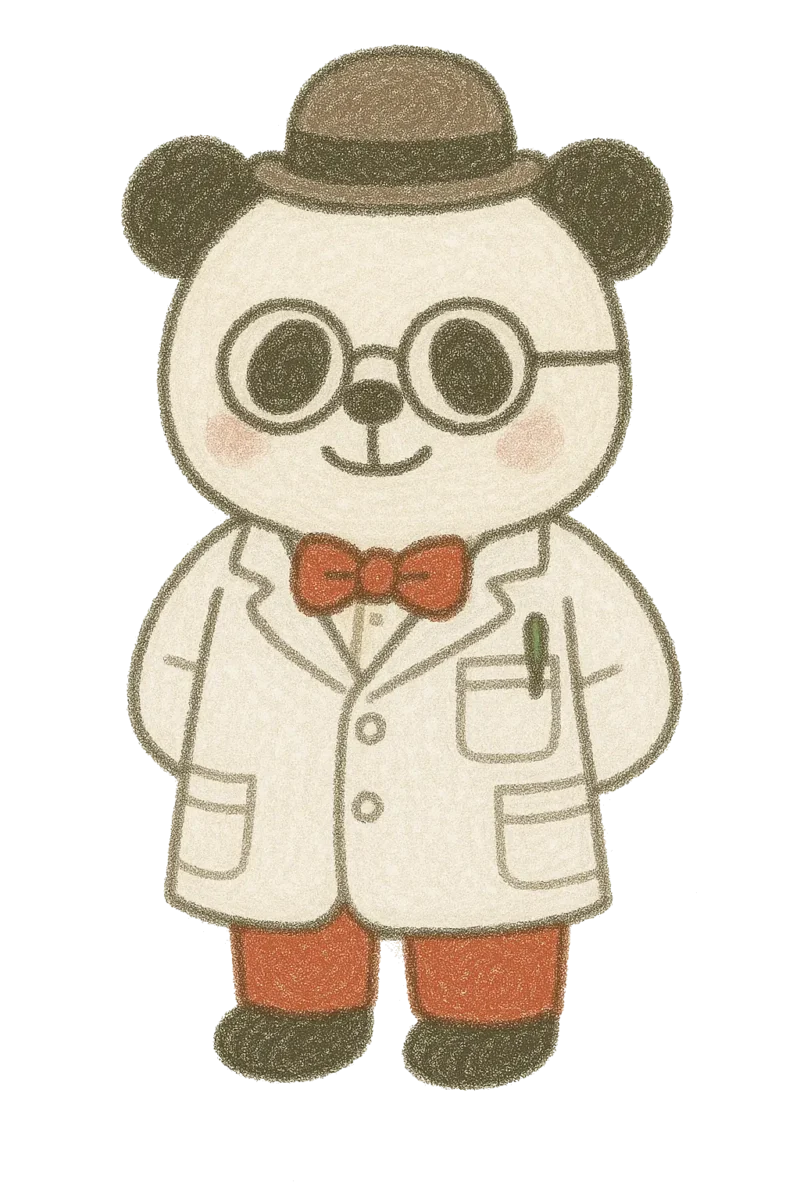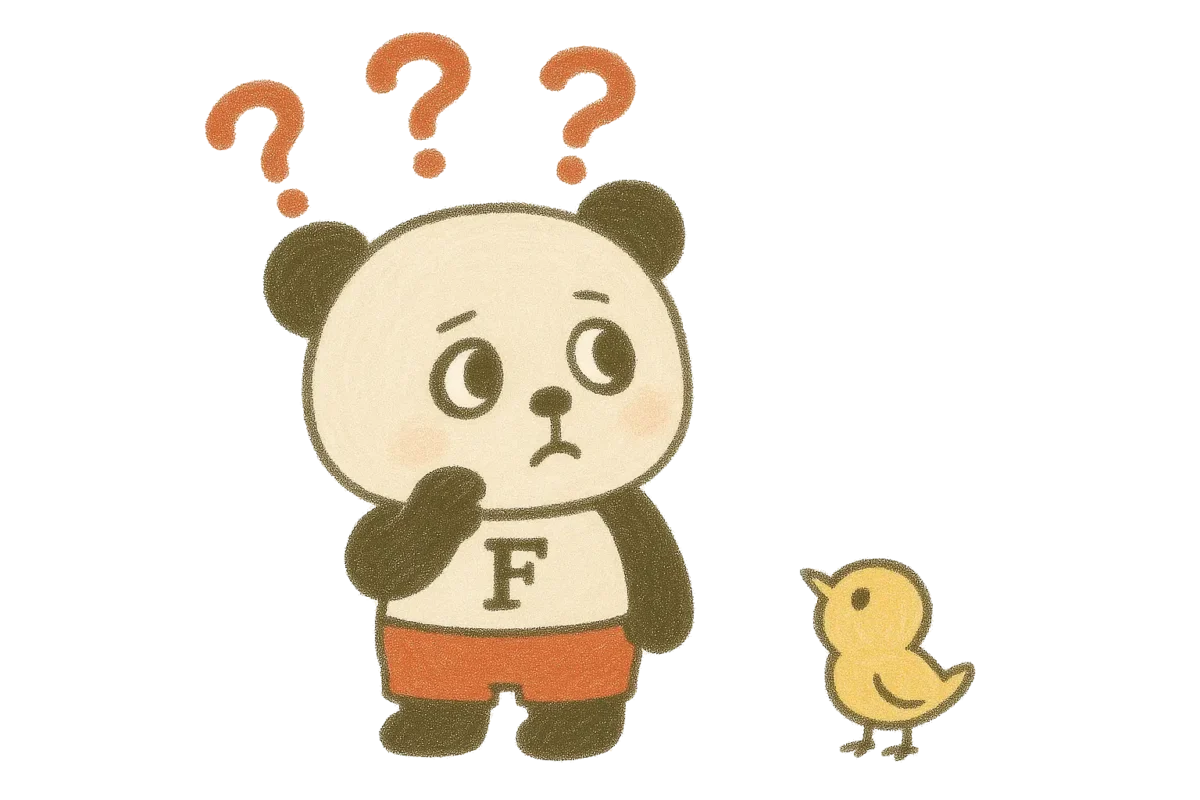わからない前提で解説
5歳でもなんとなく分かるFX用語!

STEP 01なんとなく理解しよう!
5歳でもわかる超かんたん解説
ドンチャンチャンネルっていうのはね、過去の一番高い値段と一番安い値段を線で結んだものなんだよ。
例えば、この1週間でお菓子の値段を毎日見ていたとして、一番高かった日と一番安かった日があるでしょ?その最高と最低を覚えておいて線を引くんだ。
今の値段がその最高の線を超えたら「今までで一番高い!」ってことだし、最低の線を下回ったら「今までで一番安い!」ってことがわかるよ。
トレーダーさんたちは、新しい最高値や最安値が出た時に「何か変化が起きているかも!」って注目するんだ。とってもシンプルで分かりやすい道具だよ!
つまりドンチャンチャンネルは過去の最高値と最安値を教えてくれる思い出アルバムみたいなものだよ!
ドンチャンチャンネルは過去の記録を更新したかどうかを教えてくれる便利な道具なんだ。
運動会の記録を思い出してみて。去年の最高記録があって、今年それを超えたら「新記録!」って盛り上がるでしょ?
FXでも同じで、例えば過去20日間の最高値を更新したら、みんなが「おお!新記録だ!」って注目するんだ。逆に最安値を更新したら、「これは大変だ!」ってなるんだよ。シンプルだけど、とっても大切な情報を教えてくれるんだ!

STEP 02さらに深掘ってマスターしよう!
もっと詳しい本格解説
ドンチャンチャンネル(Donchian Channel)は、リチャード・ドンチャンが開発した最もシンプルで効果的なトレンドフォロー指標の一つなんですよ。一定期間の最高値を結んだ上限線と、最安値を結んだ下限線、そしてその中間線で構成されています。
標準的な設定は20期間で、過去20日間の最高値・最安値を表示します。価格が上限線を突破すれば新高値更新で買いシグナル、下限線を突破すれば新安値更新で売りシグナルとなります。「タートルズ」という有名なトレーダー集団もこの手法を採用していました。
ドンチャンチャンネルの特徴は、計算が単純で理解しやすい点です。移動平均線のような複雑な計算は不要で、誰でも同じ結果が得られます。また、ブレイクアウト戦略に最適で、レンジ相場からトレンド相場への転換を捉えやすいという利点があります。中間線はトレンドの方向性判断にも活用できます。
関連用語をチェック!
ブレイクアウト 重要な価格水準を突き抜ける値動きで新たなトレンドの始まり タートルズ ドンチャンチャンネルを使って成功した伝説的なトレーダー集団
レンジブレイク 一定の値幅で推移していた相場が範囲を抜け出す動き
期間 ドンチャンチャンネルで参照する過去の日数
中間線 上限線と下限線の中間に位置する線

STEP 03ドンチャンチャンネルに関するQ&A
よくある質問と回答
最も一般的なのは
20期間ですが、短期取引なら10期間、中期なら20〜50期間、長期なら50〜100期間が使われます。
期間を長くするほどダマシが減りますが、
エントリーが遅れる傾向があります。
中間線は
トレンドの方向性判断に使えます。価格が中間線より上なら上昇傾向、下なら下降傾向と判断します。また、
トレンド中の押し目買い・戻り売りのポイントとしても活用できます。
最大の欠点は
レンジ相場でのダマシが多いことです。また、
ブレイクアウト後すぐに反転することもあり、
ストップロスの設定が難しいという面もあります。
トレンド相場でこそ威力を発揮します。
タートルズは
20日と55日の2つのドンチャンチャンネルを使用しました。20日ブレイクで
エントリーし、10日チャンネルの反対側でエグジット。
資金管理も徹底し、大成功を収めました。
異なる期間のチャンネルを表示することで、短期・中期・長期の
トレンドを同時に把握できます。例えば、全ての期間で上限ブレイクしたら、
非常に強い上昇トレンドと判断できます。
一般的には
エントリーと反対側のチャンネルに設定します。
買いなら下限線、
売りなら上限線です。ただし、これでは損失が大きくなることもあるので、
ATRなどを使った固定幅の
損切りと併用することもあります。