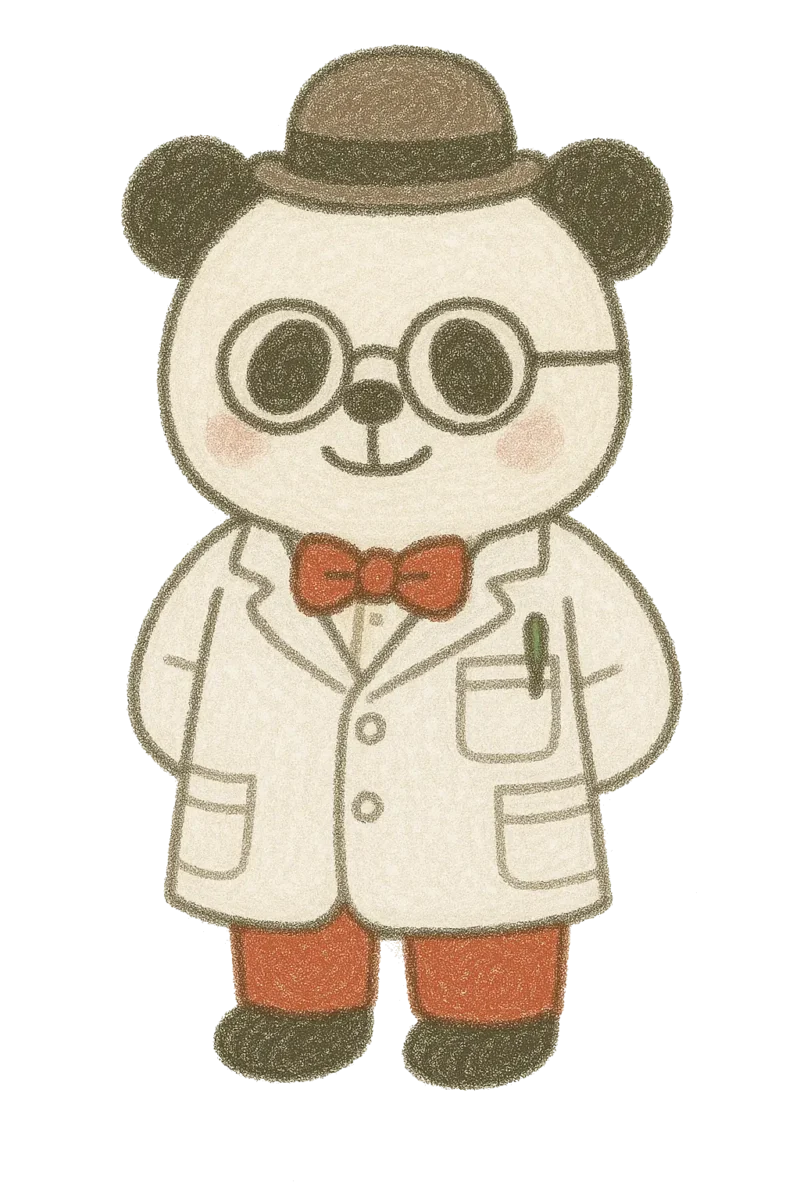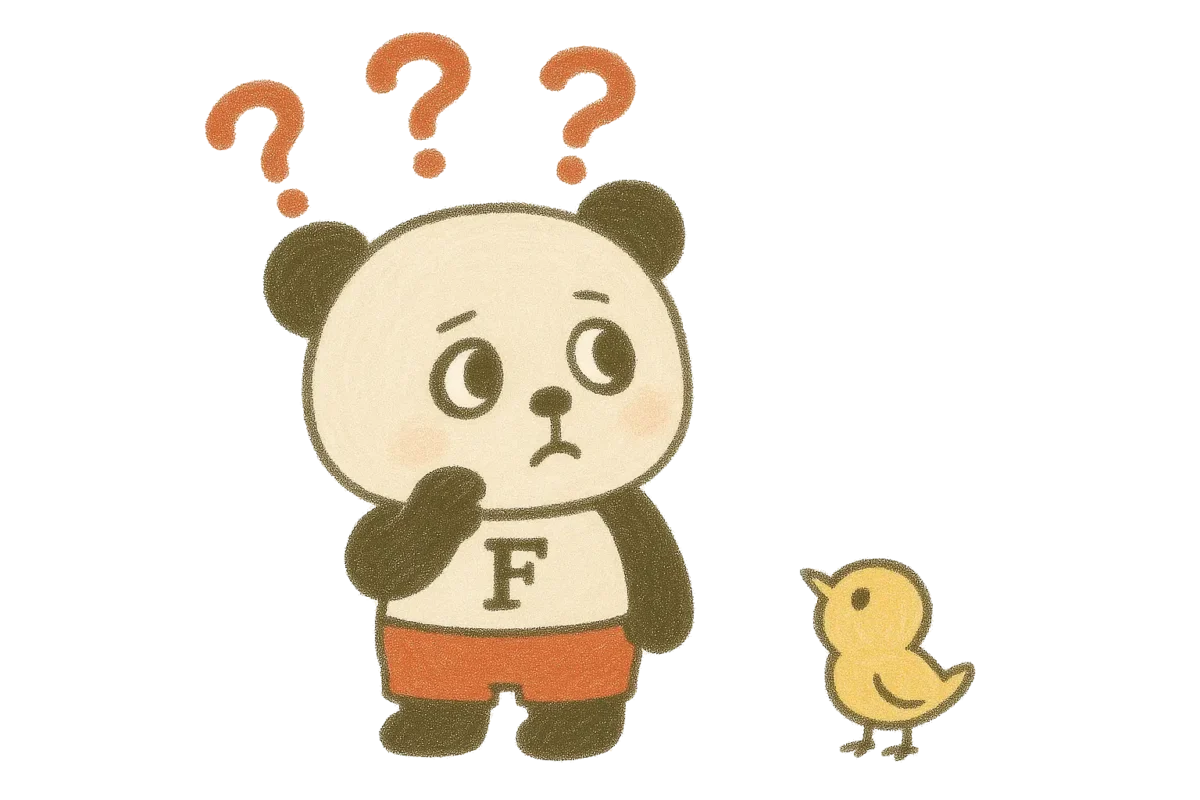わからない前提で解説
5歳でもなんとなく分かるFX用語!

STEP 01なんとなく理解しよう!
5歳でもわかる超かんたん解説
適合性原則っていうのはね、その人に合ったものを勧めるっていう大切なルールなんだよ。
たとえば、まだ泳げない子に「深いプールで泳ごう!」って言うのは危ないよね。最初は浅いプールで練習して、上手になってから深いプールに行くべきでしょ?FXも同じで、初心者には簡単なものから始めてもらうんだ。
お小遣いが少ない子に、高いおもちゃを勧めるのも良くないよね。FXの会社も、その人のお金の余裕を考えて、無理のない取引を勧めなきゃいけないんだ。
おじいちゃんにスケートボードを勧めたり、小さい子に難しい本を勧めたりしないのと同じで、年齢や経験も考えて、その人にピッタリのものを選んでもらうんだよ。
これは法律で決まっていて、もし守らないで、合わないものを無理やり勧めたら、その会社は罰せられるんだ。(みんなを守るための大切なルールなんだよ)
つまり適合性原則は「その人にピッタリのものを選ぶ」優しいルールだよ!
適合性原則は、投資家のレベルに合わせた商品を勧めるルールなんだ。ゲームで言えば、初心者にいきなり最高難易度を勧めないのと同じだよ。
FX会社は、お客さんの投資経験、お金の余裕、投資目的を聞いて、無理のない取引を提案するんだ。初心者に高レバレッジを勧めたり、お金に余裕がない人に大きな取引を勧めたりしてはいけないんだよ。これでみんなが安全に投資できるようになっているんだ。

STEP 02さらに深掘ってマスターしよう!
もっと詳しい本格解説
適合性原則は、金融商品取引法で定められた投資家保護の根幹をなす原則なんですよ。金融機関は、顧客の知識、経験、財産状況、投資目的を把握し、それに適合した商品・サービスのみを勧誘しなければなりません。
具体的には、投資経験の浅い顧客に複雑な仕組み商品を勧誘してはいけない、余裕資金の少ない顧客に高額投資を勧めてはいけない、高齢者には慎重な対応が必要、といった運用がなされています。FX取引では、レバレッジの設定も顧客の適合性に応じて制限され、初心者は低レバレッジから開始することが推奨されています。
違反した場合、業務改善命令や業務停止などの行政処分が科されます。また、不適切な勧誘により顧客が損失を被った場合、損害賠償請求の対象となる可能性もあります。これは「狭義の適合性原則」と呼ばれ、そもそも勧誘してはいけない顧客層を定めています。一方、説明方法を顧客に合わせる「広義の適合性原則」もあり、両面から投資家保護を図っているんですよ。
関連用語をチェック!
投資目的 なぜ投資するのかという顧客の目標や理由
財産状況 顧客の収入、資産、負債などの経済的状況
投資経験 過去の投資履歴や金融商品への理解度
高齢者ガイドライン 高齢投資家への勧誘に関する特別な指針
不招請勧誘 顧客が求めていないのに勧誘する行為
説明義務 金融商品のリスクや仕組みを説明する法的義務

STEP 03適合性原則に関するQ&A
よくある質問と回答
FX業者は
口座開設時のアンケートで判断します。年齢、職業、年収、金融資産、投資経験、投資目的などを質問し、総合的に評価します。
虚偽申告は禁物で、正直に答えることが自分を守ることになります。定期的に情報更新も求められます。
口座開設を断られる場合があります。これは差別ではなく、投資家保護のためです。たとえば、無職で貯金がない人や、投資経験が全くない高齢者などは断られることがあります。まずは
知識を身につけ、余裕資金を作ることが大切です。
虚偽申告で
口座開設すると、
規約違反で口座凍結される可能性があります。また、損失が出ても自己責任となり、保護を受けられません。最悪の場合、
詐欺罪に問われることもあります。正直な申告が、結果的に自分を守ることになります。
はい、経験を積めば適合性も向上します。初心者でも、少額取引で経験を積み、知識を身につければ、より高度な取引が可能になります。逆に、財産状況が悪化すれば適合性は低下します。業者は定期的に顧客情報を更新して確認しています。
高齢者には特別に慎重な対応が求められます。75歳以上は原則として複雑な商品の勧誘禁止、家族の同席推奨、録音による記録保存などのルールがあります。認知機能の低下リスクも考慮し、定期的な意思確認も行われます。高齢者保護は特に重視されています。
海外FX業者は
日本の適合性原則に縛られません。誰でも高
レバレッジ取引ができる業者も多く、投資家保護が不十分です。経験の浅い投資家が大損するケースも多いため、
自己判断での利用は危険です。日本の規制下にある業者の利用が安全です。
適合性原則は完全な保護ではありません。最終的な投資判断は自己責任です。また、オンライン取引では対面確認ができないため、申告内容の真偽確認に限界があります。投資家自身の慎重な判断が最も重要で、適合性原則はあくまで補助的な役割です。
AIを活用した
より精密な適合性判断が研究されています。取引履歴や行動パターンから、リアルタイムで適合性を評価する仕組みです。また、
ロボアドバイザーによる個別
最適化も進んでおり、より安全で効率的な投資環境の実現が期待されています。