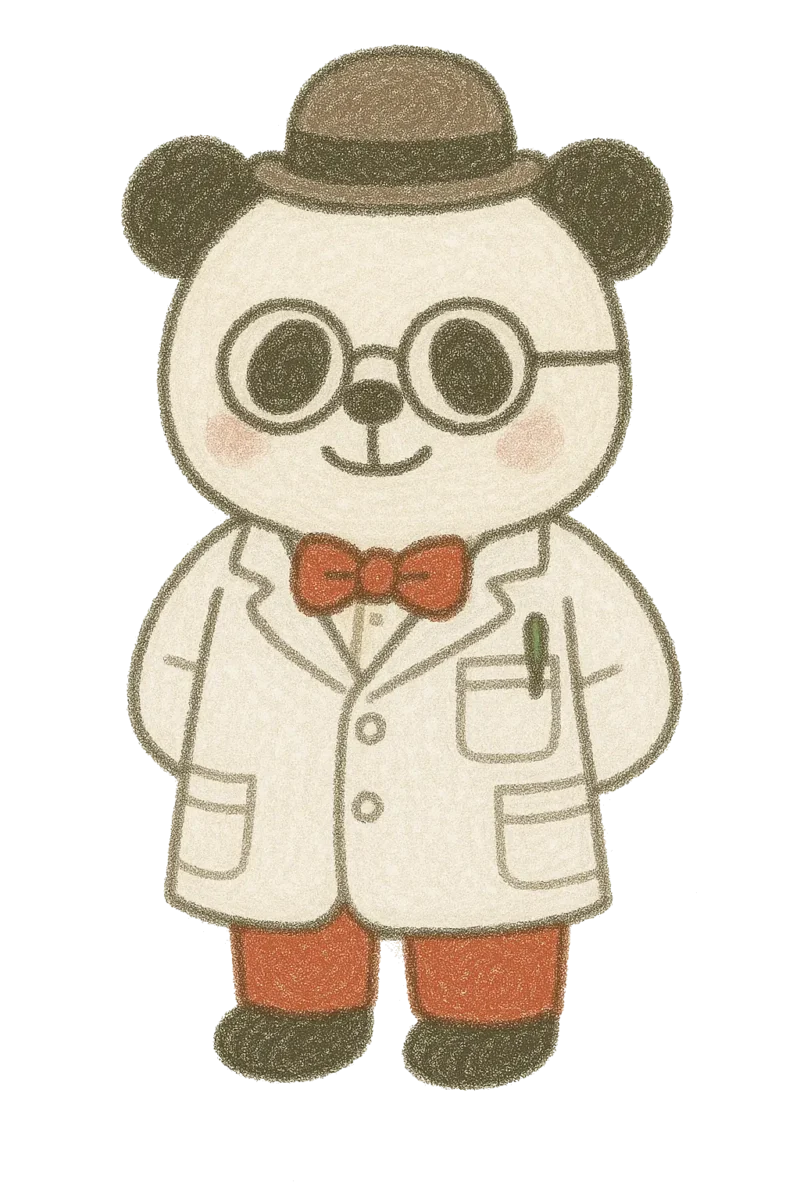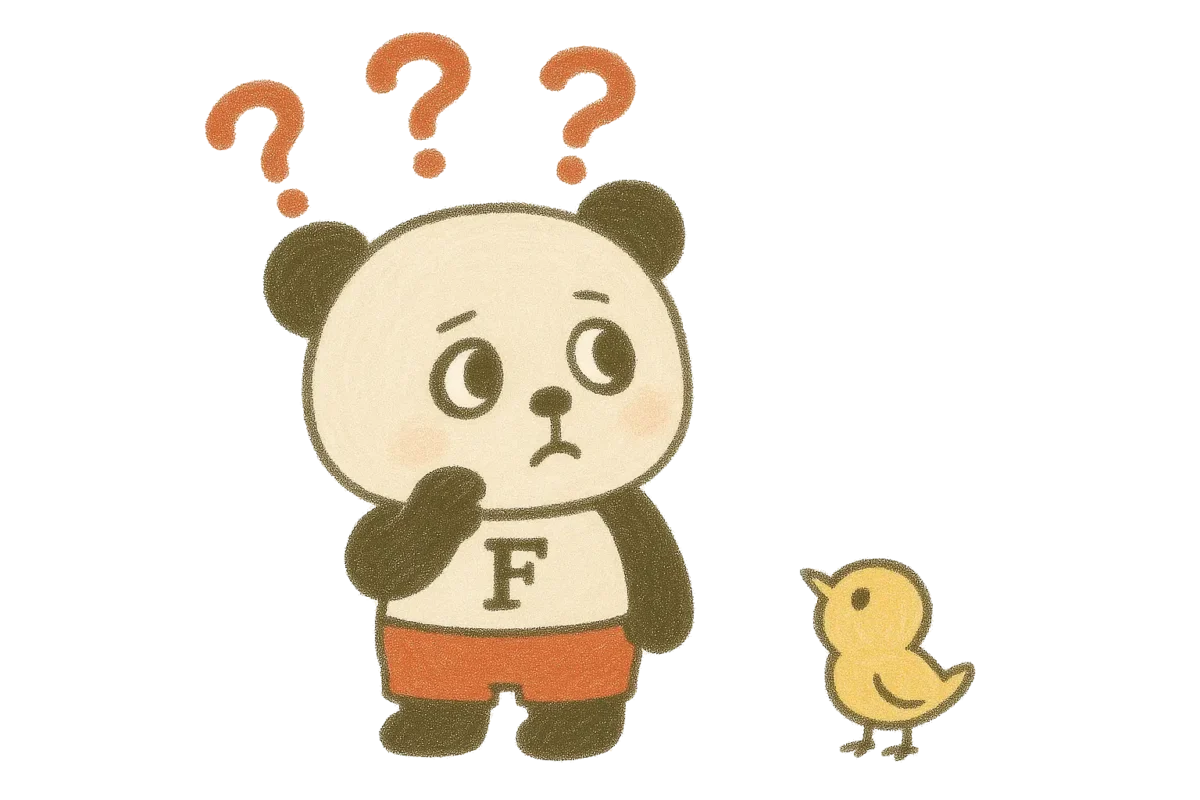わからない前提で解説
5歳でもなんとなく分かるFX用語!

STEP 01なんとなく理解しよう!
5歳でもわかる超かんたん解説
補償制度っていうのはね、もしもの時にお金を返してもらえる約束のことなんだよ。
たとえば、君が自転車で転んでケガをした時、保険に入っていれば病院代を払ってもらえるよね。それと同じように、お金を預けている会社が潰れちゃった時に、別の所からお金を返してもらえる仕組みがあるんだ。
銀行にお金を預けている時は「預金保険」、株を買っている時は「投資家保護基金」、FXをやっている時は「信託保全」っていう、それぞれ違う守り方があるんだよ。
これらの補償制度があるから、お父さんやお母さんは安心してお金を預けたり、投資したりできるんだ。もし補償制度がなかったら、会社が潰れたら全部なくなっちゃうから、みんな心配でお金を家に隠すようになっちゃうよね。
日本では、預金なら1000万円まで、投資でも1000万円まで、FXなら全額が守られているんだ。(ただし、投資で損したお金は返してくれないよ)
つまり補償制度は「もしもの時の安全ネット」みたいなものだよ!
補償制度は、金融機関が潰れても大丈夫なように作られた保険みたいなものなんだ。遊園地のジェットコースターにシートベルトがあるように、お金の世界にも安全装置があるんだよ。
銀行、証券会社、FX会社、それぞれに違う補償の仕組みがあって、みんなのお金を守っているんだ。1000万円までとか、全額とか、守ってくれる金額は違うけど、ちゃんと法律で決まっているから安心なんだよ。

STEP 02さらに深掘ってマスターしよう!
もっと詳しい本格解説
補償制度は、金融システムの安定性と投資家保護を両立させる重要な仕組みなんですよ。日本では、預金は預金保険制度、証券投資は投資家保護基金、FX取引は信託保全制度と、金融商品ごとに異なる補償制度が整備されています。
これらの制度は、金融機関の破綻から投資家を守る最後の砦として機能します。預金保険は1金融機関1預金者あたり元本1000万円とその利息、投資家保護基金は1顧客1000万円まで、FXの信託保全は全額が保護されます。ただし、いずれも投資損失は補償対象外で、あくまで金融機関の破綻や不正から守る制度です。
国際的にも補償制度は重要視されており、各国で独自の制度が構築されています。ただし、補償額や対象範囲は国により大きく異なるため、海外投資の際は事前確認が必須です。また、暗号資産など新しい金融商品については、補償制度が未整備な部分もあり、今後の課題となっています。
関連用語をチェック!
預金保険制度 銀行預金を1000万円まで保護する日本の制度
信託保全 FX業者が顧客資産を信託銀行で全額保護する制度 ペイオフ 金融機関破綻時に預金保険で保護される仕組み 預金保険機構 日本の預金保険制度を運営する認可法人
金融ADR 金融トラブルを裁判外で解決する制度
システミックリスク 一つの破綻が連鎖的に広がるリスク
モラルハザード 補償があることで生じる過度なリスクテイク

STEP 03補償制度に関するQ&A
よくある質問と回答
日本の主な補償制度は
預金保険、投資家保護基金、信託保全の3つです。預金保険は銀行預金を1000万円まで、投資家保護基金は証券投資を1000万円まで保護します。FXの信託保全は全額保護です。また、
保険契約者保護機構もあり、生命保険は責任準備金の90%が補償されます。
多くの場合、
自動的に補償手続きが開始されます。預金保険や
投資家保護基金は、金融機関の破綻が決定すると自動的に手続きが始まります。顧客は案内に従って必要書類を提出するだけです。FXの
信託保全も、
信託管理人が手続きを代行してくれるので、複雑な手続きは不要です。
補償制度は金融機関の破綻による損失のみ対象で、投資の失敗による損失は補償されません。また、外貨預金や仕組み預金など一部の金融商品は対象外です。さらに、1000万円を超える部分や、反社会的勢力の資産も補償対象外となります。
海外の金融機関は各国独自の補償制度が適用されます。米国のFDIC(連邦預金保険公社)は25万ドル、EUの預金保証は10万ユーロなど、国により補償額が異なります。日本の制度は適用されないため、海外投資では現地の制度を必ず確認する必要があります。
補償制度の財源は
金融機関が支払う保険料や負担金です。預金保険料は預金残高に応じて銀行が支払い、
投資家保護基金は証券会社が負担金を拠出します。これらは最終的に手数料などに転嫁される可能性がありますが、
顧客が直接支払うことはありません。
現在、暗号資産は
既存の補償制度の対象外です。ただし、改正資金決済法により、暗号資産交換業者は顧客資産の
分別管理が義務付けられています。一部の業者は独自の補償制度を設けていますが、
法的な補償制度は未整備で、今後の課題となっています。
同一金融機関の複数口座は名寄せされて合算されます。たとえば、同じ銀行に普通預金500万円と定期預金600万円がある場合、合計1100万円のうち1000万円までが保護されます。一方、別の金融機関なら各1000万円まで保護されるため、リスク分散が推奨されます。
デジタル化の進展により、
新しい金融サービスへの対応が課題です。
DeFi(分散型金融)や
ステーブルコインなど、既存の枠組みに収まらない商品が増えています。また、
国際的な補償制度の連携も重要で、クロスボーダー取引の増加に対応した制度設計が求められています。