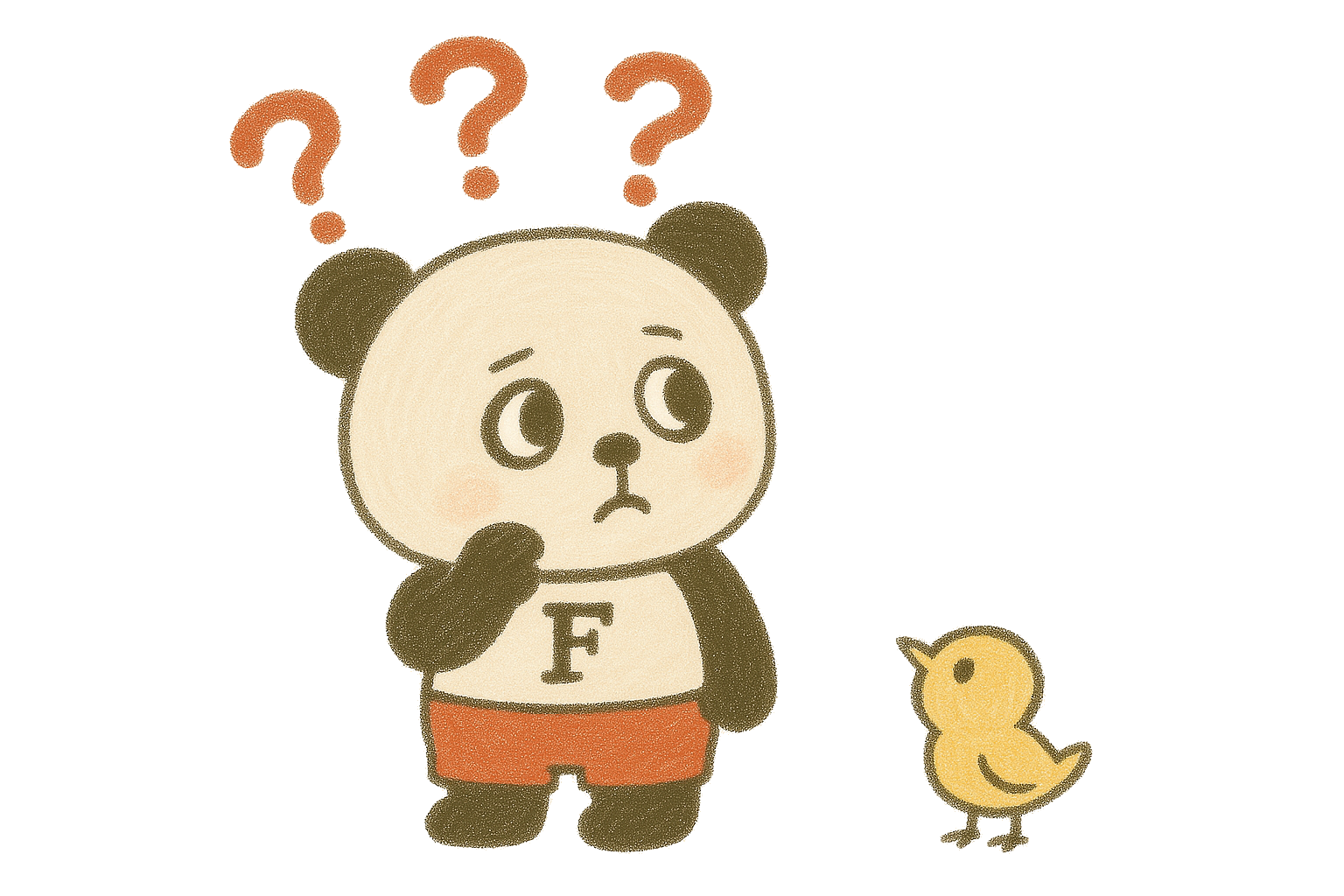わからない前提で解説
5歳でもなんとなく分かるFX用語!

STEP 01 なんとなく理解しよう!
5歳でもわかる超かんたん解説
タカ派・ハト派っていうのはね、お金の管理をする人たちの考え方を鳥に例えた言葉なんだよ。
タカは強くて厳しい鳥でしょ?タカ派の人は「お金を使いすぎないように厳しくしよう」って考える人たちなんだ。反対に、ハトは優しい鳥だから、ハト派の人は「みんなが困らないように優しくしよう」って考えるんだよ。
例えば、お小遣いをたくさんあげるのがハト派のお母さん、厳しく管理するのがタカ派のお父さんみたいな感じかな。
どっちがいいか悪いかじゃなくて、その時々で必要な考え方が違うんだよ!(経済の状態によって変わるんだ)
つまりタカ派とハト派は厳しいお父さんと優しいお母さんみたいな違いだよ!
タカ派とハト派は金利を上げたい人と下げたい人の違いなんだ。
学校の規則を考えてみて。規則を厳しくしたい先生と、もっと自由にしたい先生がいるでしょ?それと同じで、タカ派は「金利を上げて引き締めよう」、ハト派は「金利を下げて緩めよう」って考えるんだ。
景気が良すぎる時はタカ派の出番、景気が悪い時はハト派の出番って感じで、経済のバランスを取るために両方の考え方が必要なんだよ!

STEP 02 さらに深掘ってマスターしよう!
もっと詳しい本格解説
タカ派(Hawkish)とハト派(Dovish)は、中央銀行関係者や金融政策決定者の政策スタンスを表す比喩的な表現なんですよ。タカ派は金融引き締めに積極的、ハト派は金融緩和に積極的な立場を指します。
タカ派はインフレ抑制を重視し、利上げに前向きな姿勢を取ります。物価安定を最優先し、景気過熱やバブルを警戒します。一方、ハト派は雇用や経済成長を重視し、利下げや緩和策に前向きです。景気後退のリスクを懸念する傾向があります。
重要なのは、同じ人物でも経済状況によってスタンスが変わることです。中央銀行は物価安定と雇用最大化の両方を目指すため、状況に応じて適切なバランスを取る必要があります。市場は要人発言や議事録から、政策決定者のスタンスの変化を読み取ろうとします。
関連用語をチェック!
金融緩和 金利引き下げなどで経済活動を刺激する政策 中立派 タカ派でもハト派でもない中間的な立場
利上げ 政策金利を引き上げる金融引き締め策
利下げ 政策金利を引き下げる金融緩和策
要人発言 中央銀行関係者など重要人物の発言
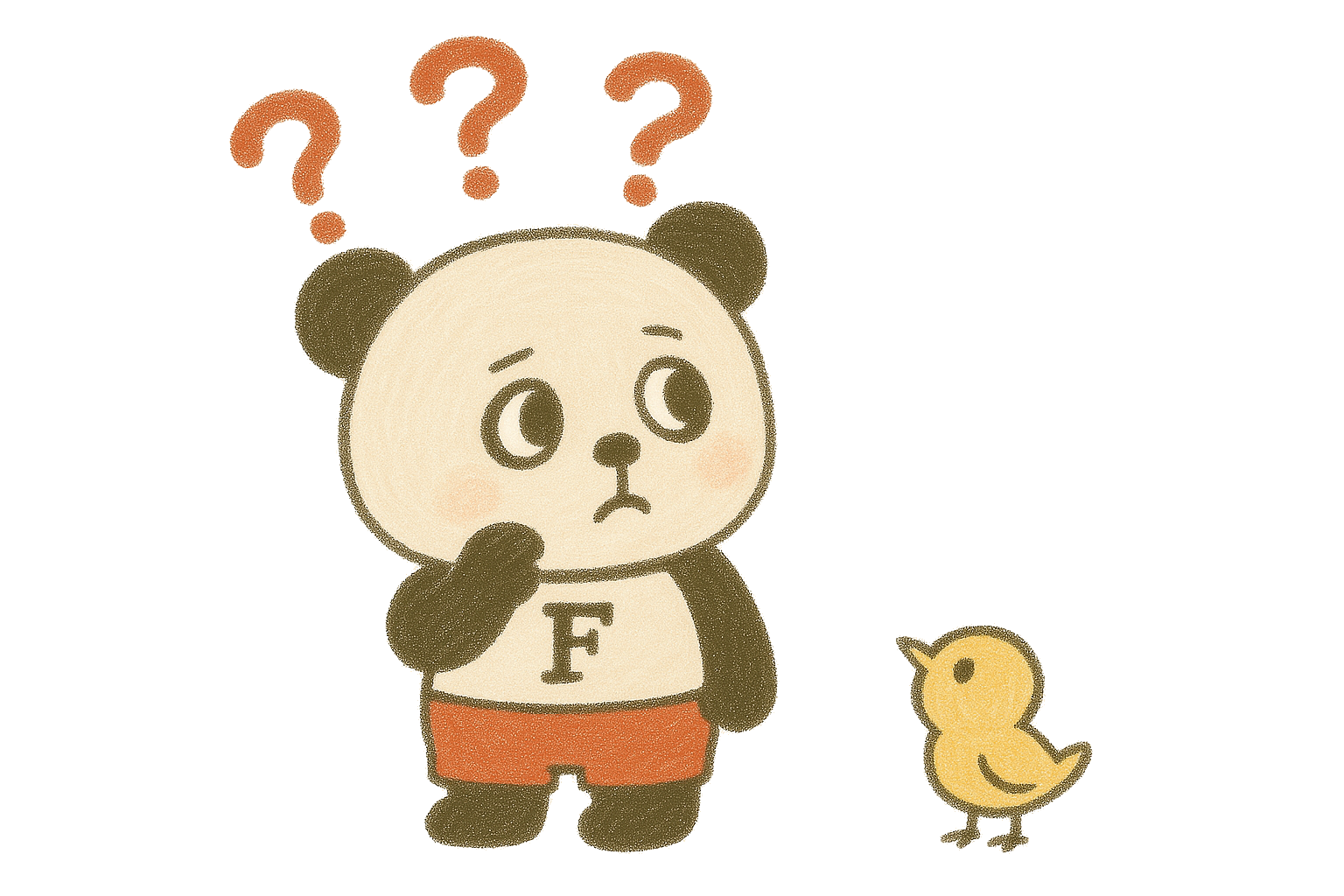
STEP 03 タカ派・ハト派に関するQ&A
よくある質問と回答
タカは攻撃的で強い鳥、ハトは平和的で穏やかな鳥というイメージから来ています。もともとは政治用語で、戦争に対する姿勢を表していましたが、金融政策にも使われるようになりました。
どちらが正しいということはなく、経済状況に応じて適切なスタンスがあります。インフレ時はタカ派的政策、不況時はハト派的政策が必要です。バランスが重要なんです。
発言内容に注目します。「インフレリスク」「引き締め」などの言葉が多ければタカ派的、「景気下振れ」「緩和的」などが多ければハト派的です。過去の投票行動も参考になります。
データ次第でどちらにも動ける柔軟な立場の人を指します。特定の方向性に偏らず、
経済指標を見て判断します。市場では
最も予測が難しい存在とされています。
一般的に
その国の通貨は上昇します。利上げ期待が高まり、
金利差拡大を見込んだ資金が流入するためです。ただし、
すでに織り込まれている場合は反応が限定的なこともあります。
非常に重要です。投票権を持つメンバーの構成で政策の方向性が変わります。タカ派が多数なら利上げしやすく、ハト派が多数なら緩和的な政策が維持されやすくなります。
もちろんいます。政策委員会のメンバーそれぞれにスタンスがあり、金融政策決定会合での投票行動に表れます。議事要旨を読むと、各委員の考え方がわかります。
いいえ、経済状況や役職によって変化します。以前ハト派だった人が、インフレ懸念からタカ派に転じることもあります。これを「タカ派転向(Hawkish turn)」と呼びます。