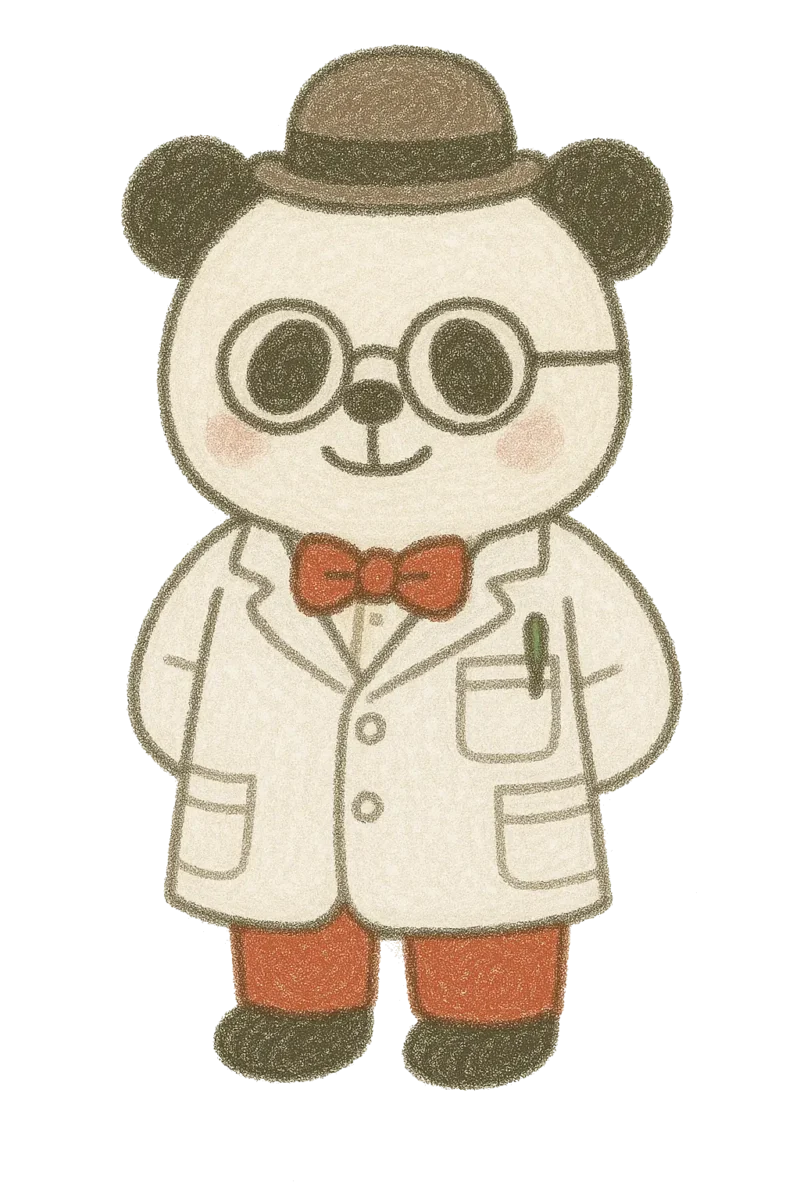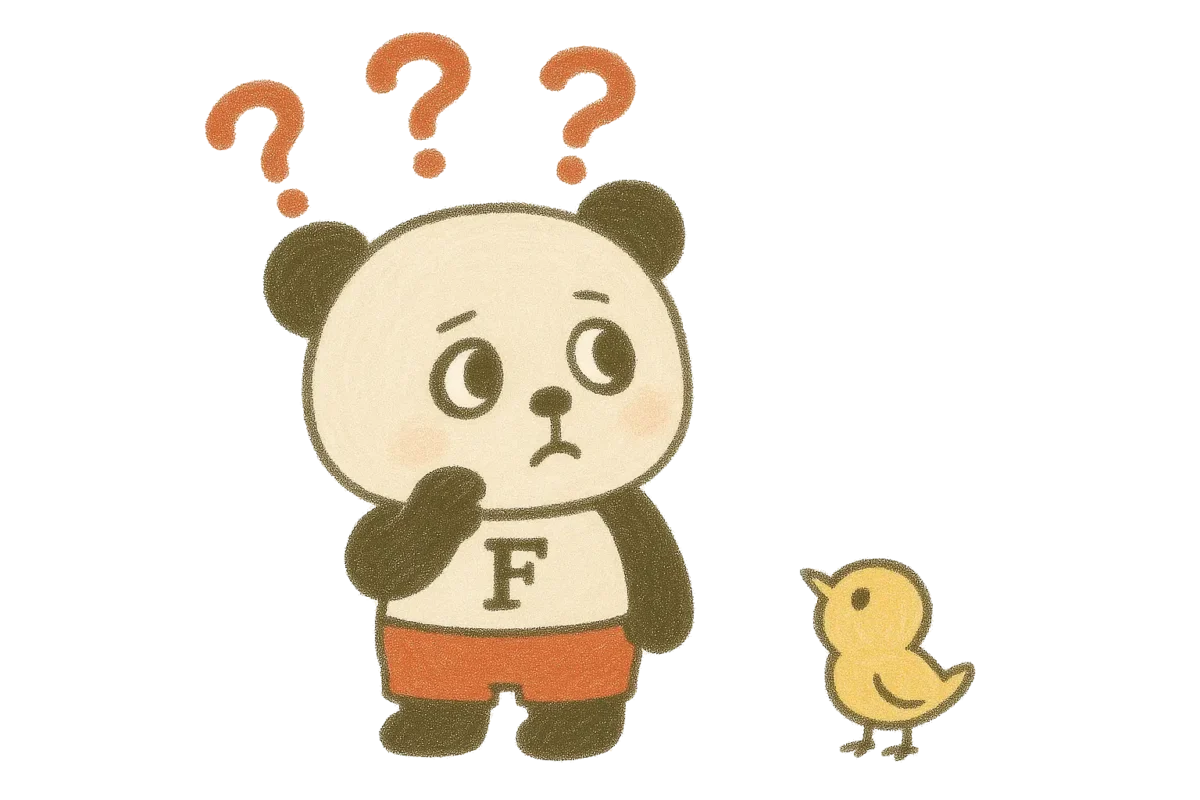わからない前提で解説
5歳でもなんとなく分かるFX用語!
もくじ
STEP 01 なんとなく理解しよう! 5歳でもわかる超かんたん解説
ECBっていうのはね、ヨーロッパのお金(ユーロ)を管理する大きな銀行 のことなんだよ。みんなで同じ「ユーロ」というお金 を使っているんだ。でも、たくさんの国が同じお金を使うと、誰が管理するか困っちゃうよね。みんなのお金を守る役割 をしているんだよ。物の値段が上がりすぎないように見張ったり、お金の量を調整したりして、ヨーロッパの人たちが安心してお金を使える ようにしているんだ。学級委員長がクラスをまとめるみたいに、ECBがヨーロッパのお金をまとめているんだよ。
つまりECBはヨーロッパのお金の守護神みたいな銀行だよ! ECBはユーロという共通のお金の管理人 なんだ!たくさんの国が集まって一つのチームを作るとき、キャプテンが必要だよね?ECBはまさにユーロチームのキャプテン なんだよ。ドイツもフランスもイタリアも、みんなユーロを使っているから、ECBが「今日はお金をもっと出そう」とか「ちょっと締めよう」とか決めて、みんなが幸せに暮らせる ように頑張っているんだ。
STEP 02 さらに深掘ってマスターしよう! もっと詳しい本格解説
ECB(European Central Bank/欧州中央銀行 )は、ユーロ圏の金融政策を一元的に担う超国家的な中央銀行 なんですよ。1998年に設立され、本部はドイツのフランクフルトにあります。現在20カ国が加盟するユーロ圏の物価安定を最優先目標 とし、インフレ率を「2%に近いがやや下回る水準」に維持することを目指しています。
ECBの主要な政策手段は政策金利 の決定金利 、預金ファシリティ金利、限界貸出ファシリティ金利の3つを設定します。また、量的緩和(QE) などの非伝統的金融政策も実施し、国債や社債の購入を通じて市場に流動性を供給します。政策理事会は6週間ごと に開催され、その決定は世界の金融市場に大きな影響を与えます。
ECBの特徴は、複数国の利害を調整 しながら政策決定を行う必要があることです。ドイツのような経済が堅調な国と、南欧の経済が脆弱な国では最適な金融政策が異なるため、バランスの取れた判断 が求められます。総裁の記者会見での発言は、ユーロの方向性 を占う重要な材料となるんですよ。
関連用語をチェック! FRB(連邦準備制度) 米国の中央銀行で、ECBと並ぶ世界の主要中央銀行
政策金利 ECBが設定する金利で、ユーロ圏の金融政策の基準となる 量的緩和(QE) ECBが実施する非伝統的金融政策で、資産購入により流動性を供給
インフレターゲット ECBが目標とする物価上昇率で、2%近辺を目指している
ドラギ前総裁 「何でもやる」発言で有名な元ECB総裁で、ユーロ危機を救った
ラガルド総裁 現ECB総裁で、元IMF専務理事の経歴を持つ
ユーロシステム ECBと各国中央銀行で構成されるユーロ圏の中央銀行制度
STEP 03 ECB(欧州中央銀行)に関するQ&A よくある質問と回答
Q1 ECBの政策決定はいつ行われる? → Q2 ECBの政策はユーロにどう影響する? → Q3 ECBとFRBの違いは何? → Q4 なぜECBの決定は難しいの? → Q5 ECBの量的緩和(QE)とは? → Q6 ラガルド総裁の特徴は? → Q7 ECBの「フォワードガイダンス」とは? → Q8 ユーロ圏の構造問題とECBの関係は? →
6週間ごとに年8回 、政策理事会が開催されます。通常は木曜日に開催され、
日本時間20:45(夏時間)または21:45(冬時間) に
政策金利 が発表されます。その後、
21:30から総裁記者会見 が行われ、政策の背景説明や今後の見通しが示されます。この時間帯はユーロが大きく動くため要注意です。
利上げはユーロ高要因 、利下げはユーロ安要因 となります。また、量的緩和の拡大はユーロ安、縮小はユーロ高につながります。さらに重要なのは総裁の発言 で、タカ派(引き締め的)な発言はユーロ高、ハト派(緩和的)な発言はユーロ安を招きます。市場の期待との乖離 が大きいほど、反応も大きくなります。
目標が異なります 。ECBは物価安定のみが目標ですが、FRBは物価安定と完全雇用の二つの使命があります。また、ECBは20カ国の合意形成 が必要で意思決定が複雑ですが、FRBは単一国家のため迅速な対応が可能です。政治的独立性 はECBの方が強いとされています。
経済格差が大きい国々 をまとめて管理するからです。ドイツのような強い経済国には引き締めが適切でも、ギリシャのような国には緩和が必要というジレンマ があります。また、財政政策は各国バラバラ なのに、金融政策だけ統一されているという構造的な問題もあります。
国債や社債を大量購入 して市場に資金を供給する政策です。2015年から本格的に開始され、毎月数百億ユーロ規模で資産を購入しました。目的は
デフレ脱却とインフレ率2%達成 です。購入は各国の
GDP 比率に応じて配分され、
ドイツ国債 が最も多く購入されました。現在は段階的に縮小されています。
政治的手腕と対話力 が強みです。法律家出身で元IMF専務理事という
異色の経歴 を持ち、伝統的な
中央銀行 家ではありません。
気候変動対策 を金融政策に組み込むなど、新しい視点を導入しています。市場との対話を重視し、分かりやすい言葉で政策を説明する姿勢が評価されています。
将来の金融政策の方向性 を事前に示すコミュニケーション手法です。「相当期間、現在の
金利 水準を維持する」などの
時間軸政策 や、「インフレ率が2%に到達するまで」といった
条件付きガイダンス があります。市場の予測可能性を高め、政策効果を強化する狙いがあります。
金融政策は統一、財政政策は各国バラバラ という構造的矛盾があります。ECBは金融政策しか持たないため、財政統合なき通貨統合 の限界に直面することがあります。ユーロ危機時には、本来の権限を超えて「最後の貸し手」 として行動し、政治的な批判も受けました。構造改革は各国の責任とされています。