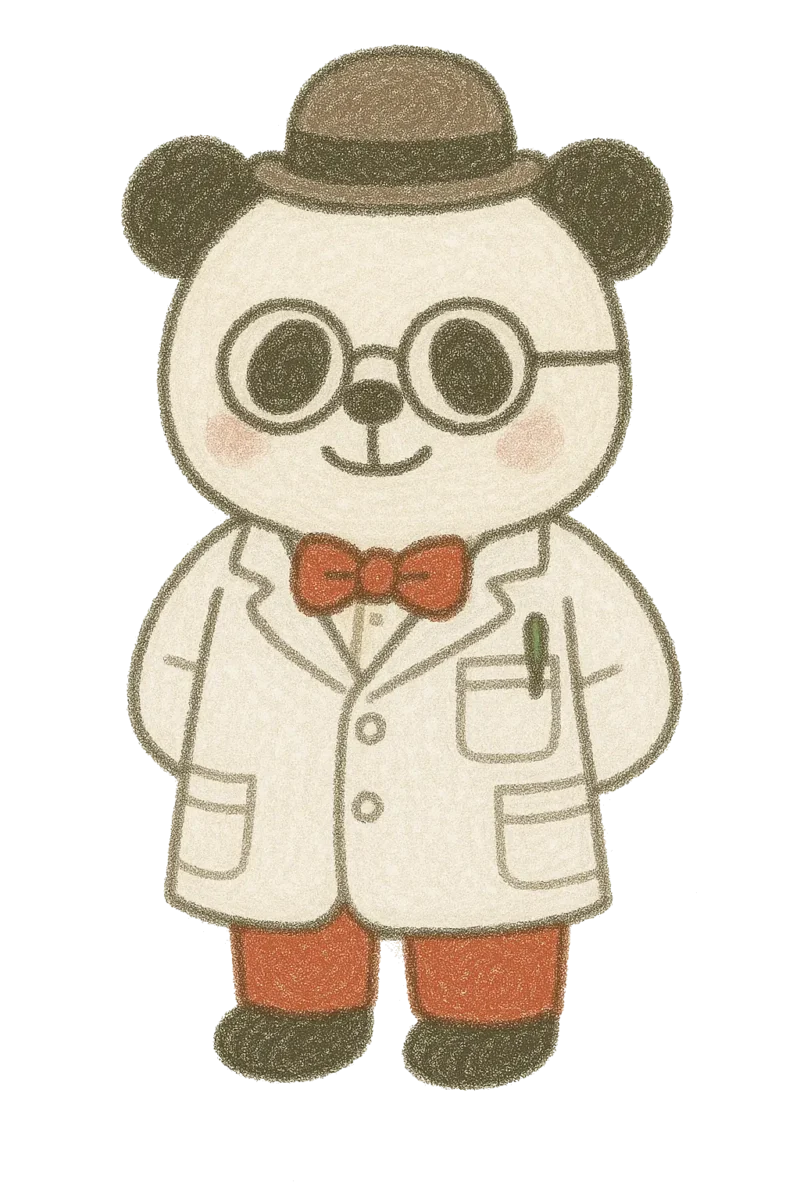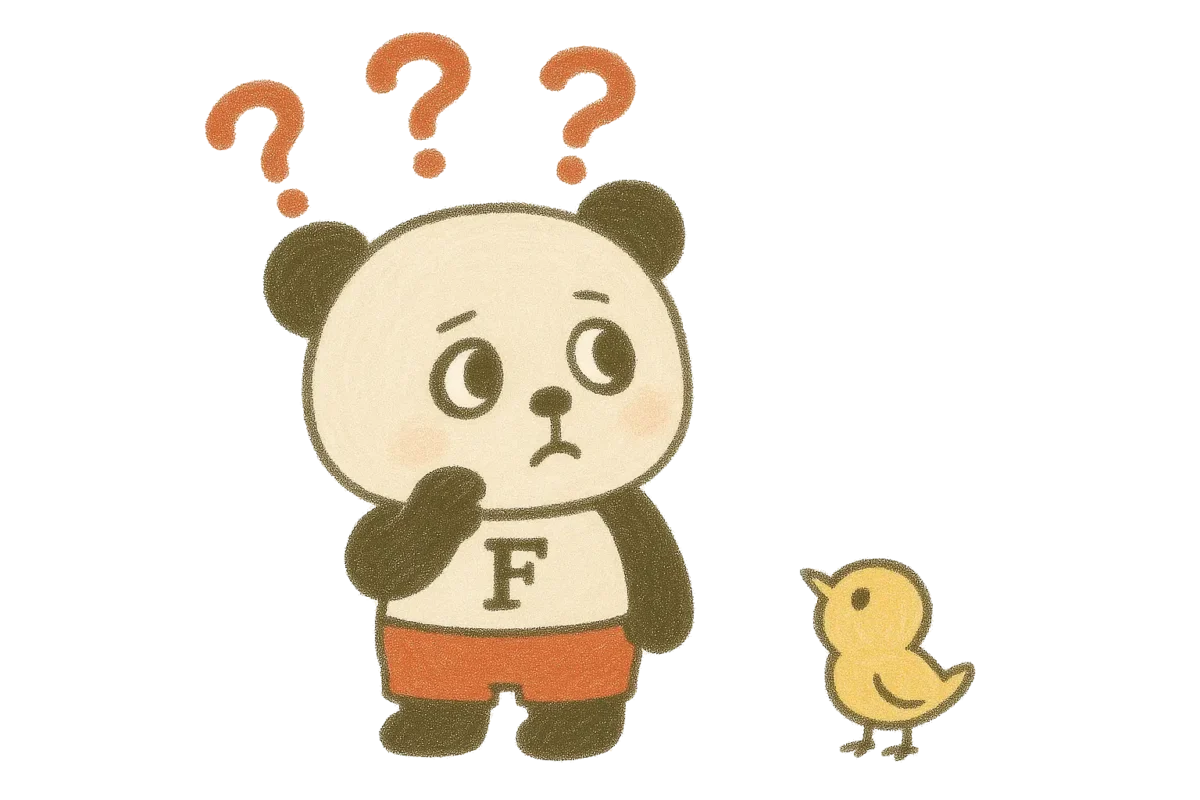わからない前提で解説
5歳でもなんとなく分かるFX用語!
金融緩和
中央銀行が金利引下げや資金供給で景気刺激する政策

STEP 01なんとなく理解しよう!
5歳でもわかる超かんたん解説
金融緩和っていうのはね、国の偉い人たちが「みんながお金を使いやすくする魔法」をかけることなんだよ。
たとえばね、君がお小遣いを貯金箱に入れても、全然増えなかったらつまらないでしょ?だから貯金しないで、おもちゃを買ったり、お菓子を買ったりするよね。それと同じなんだ。
金融緩和をすると、銀行にお金を預けてもほとんど増えないから、みんなそのお金で買い物をしたり、会社を大きくしたりするんだ。すると、景気が良くなるんだよ。
あとね、お金をたくさん刷って、世の中に出回るお金を増やすこともあるんだ。お金がたくさんあると、みんな使いやすくなるでしょ?
でも、やりすぎるとお金の価値が下がっちゃうこともあるから、ちょうどいい加減が大切なんだ。料理の味付けと同じだね。
つまり金融緩和はお金を使いやすくして景気を元気にする魔法だよ!
金融緩和は、国の中央銀行がお金の蛇口を開くようなものなんだよ。
暑い夏の日に、公園の水飲み場の蛇口をひねると水がたくさん出てくるでしょ?それと同じで、経済が元気がない時に、中央銀行がお金の蛇口を開いて、たくさんのお金を世の中に流すんだ。
お金がたくさんあると、お店も「新しい商品を作ろう!」って元気になるし、お父さんお母さんも「ちょっと贅沢してもいいかな」って思うようになる。すると、みんなが元気になって景気が良くなるんだよ。
日本やアメリカ、ヨーロッパの偉い人たちも、この魔法をよく使っているんだ。

STEP 02さらに深掘ってマスターしよう!
もっと詳しい本格解説
金融緩和は、中央銀行が金融市場に潤沢な資金を供給し、経済活動を活性化させる政策なんですよ。主な手段として、政策金利の引き下げ、量的緩和(QE)、マイナス金利政策などがあります。
具体的には、中央銀行が国債などを大量購入することで市場に資金を供給し、金利を低下させます。企業は低金利で資金調達しやすくなり、設備投資が促進されます。個人も住宅ローンなどを組みやすくなり、消費が活発化するという仕組みです。
FX市場への影響は顕著で、金融緩和を実施した国の通貨は下落圧力を受けます。金利が下がると、その通貨の魅力が低下し、投資家は他の高金利通貨へ資金を移すからです。日銀の異次元緩和で円安が進んだのも、この原理によるものです。ただし、過度な緩和はインフレリスクも孕んでいることを忘れてはいけません。
関連用語をチェック!
金融引き締め 金利引上げなどで過熱した経済を冷やす緩和の反対政策 量的緩和(QE) 中央銀行が国債等を購入して資金供給する非伝統的政策
政策金利 中央銀行が決定する短期金利で金融政策の基準 中央銀行 国の金融政策を担う銀行の銀行(日銀、FRB等) 流動性 市場に出回る資金の量で緩和により増加
金利低下 金融緩和の主要な効果で借入コストが下がる 
STEP 03金融緩和に関するQ&A
よくある質問と回答
基本的に
通貨安要因となります。
金利が下がるとその通貨の魅力が低下し、投資家は売却して他の
高金利通貨に乗り換えます。また、資金供給量が増えることで通貨の希少性が下がることも要因です。ただし、
他国も同時に緩和している場合は、相対的な影響は限定的になります。
日銀は2013年から
異次元の金融緩和を継続しています。マイナス
金利政策、イールドカーブコントロール(長短金利操作)、ETF購入など、他国に例を見ない大胆な政策を実施。結果として長期間の
円安傾向が続いていますが、
出口戦略の難しさも指摘されています。
政策金利がゼロ近辺まで下がった後の
追加緩和手段です。
中央銀行が国債や社債、ETFなどを大量購入し、市場に直接資金を供給します。2008年の金融危機後、各国が導入した非伝統的政策で、FRBのQE1〜QE3が有名です。通常の
金利政策より
強力な効果が期待されます。
主なデメリットは
インフレリスクと
資産バブルです。過剰な資金供給は物価上昇を招き、国民生活を圧迫する可能性があります。また、低
金利環境下では投資資金が株式や不動産に流れ込み、バブルを形成するリスクも。さらに、
出口戦略の困難さも大きな課題です。
金融緩和は
中央銀行による金融政策、
財政政策は政府による予算政策です。金融緩和は
金利や通貨供給量をコントロール、財政政策は公共投資や減税などで需要を創出します。両者を組み合わせる「
ポリシーミックス」が効果的とされています。
金融緩和の
正反対の政策で、過熱した経済を冷やすために実施されます。
政策金利の引き上げ、資産購入の縮小(テーパリング)、保有資産の売却などが主な手段です。インフレ抑制が目的ですが、
急激な引き締めは景気後退を招くリスクもあります。
金融引き締め(金融タイト化)が反対の政策です。
中央銀行が
金利を引き上げたり、市場から資金を吸収したりして、経済活動を抑制します。インフレが加速している時や、資産バブルの懸念がある時に実施されます。通貨は引き締めにより上昇圧力を受けます。
永続的な継続は困難です。いずれインフレ圧力が高まり、引き締めが必要になります。また、緩和に慣れた市場は、正常化の過程で大きく動揺する可能性があります。
日銀の長期緩和からの出口戦略が注目されているのも、この難しさゆえです。
段階的で慎重な正常化が求められます。